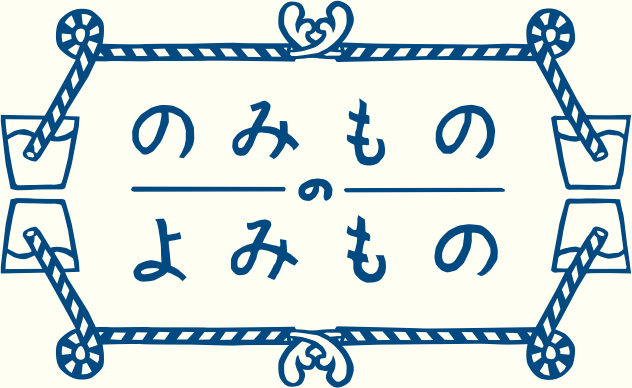

友桝飲料 代表取締役社長

こどもびいるの発案者
元もんじゃ鉄板焼下町屋店主
有限会社ウィロー代表

それが下町屋さんはものすごく売れるんですけども、卸業者さんや酒屋さんには全く売れず、高い!と言われて営業は返り討ちにあって帰ってきてました。しばらくは苦戦しましたね。
僕ら外から見ると飲料が安すぎるんですよね。飲食店では100円で買ったら380円で売り、1本で280円の利益を出します。最初に僕が断られた飲料メーカーは後につぶれたそうですが、そこは大量生産で1ケース何十円の利益だったらしくて。製造のプロが1万本製造して得る利益と素人が140本ほど売って得る利益が同じ…、商売としてどちらが正しいんだろうって思いました。
だから「こどもびいる」は大切に売っていきたかった。そもそも最初は「下町屋に来てもらうためのツール」として作ったような商品だったから、コンビニで買えるようになったら意味がないんで。今でもこんなやり方は珍しいと思うけど「酒屋やスーパーでの小売はしない。基本的には飲食店のみに卸す」という方針で販売してもらっています。
商品もそうですが、売り方も今までにない売り方だったんです。だからすぐに理解してもらえなくても仕方ないなと思っていました。バイヤーさんたちが「こどもびいる」を飲む様子も見てないし、コンセプトも意図も伝わりにくいだろうなと。
それはなかったです。浅羽さんから依頼が来てすぐに会いに行ったのも、浅羽さんと同様に僕も「こどもびいる」が良い商品だなと思ったからなんです。今も半年、10年、温めている商品というのはありますが、売れるか売れないかは、時の運というところがあると思っています。



面白いと感じたものを面白がり続けることは、簡単なようで実は一番難しいことなのかもしれません。小さな応接テーブルの上で、時に下町屋のテーブルの上で、何度も打合せを重ねていきます。
まあ、逆に僕はあんまり売れてほしくなくて(笑)。飲料業界では「センミツ」という言葉があって、毎年千(セン)を超える商品ができて翌年に残るのは3つ(ミツ)くらいと言われるほど厳しい世界だから。「こどもびいる」を一時的にヒットして消えてしまう商品にはしたくなかったんで、瞬間的なヒットではなくて、ジワジワと売れる商品になってほしかったんです。
イラストになっているのは、長男と長女、愛犬の万次郎。当時、友人だったイラストレーターの八智代(のちの妻であり現在、仕事のパートナーでもある)が描き下ろしてくれたもの。僕の子どもたちが親になった時にどこかの飲食店で『これはじいちゃんが作ったと』とか、もっといえば『ひいじいちゃんが作った』と言って欲しかったから。それは社長も一緒ですよね。子どもや孫が飲んだ時にそういうものを感じることができるよう「長く売れ続ける商品」にしたいなと思ったんです。
そうですね。ポスターにある「子どもだって、のまなきゃ、やってらんねーよ」というキャッチコピーもいいですよね。当時は配達のトラックにこのキャッチコピーを描いて走っていました。地元ではちょっとした噂になっていましたよ(笑)
その後、2005年フーデックスという初めての展示会に出展したところ、百貨店の人やバイヤーさんがビックリするくらい来てくれて手応えを感じたんです。90cm角の小さいブースに社長と八智代と3人で並んでたんだけど、隣のブースまで人があふれちゃうくらいで。分かる人には分かるんだなーと(笑)




楽しいなと思ったことを夢中になって楽しむ、そんな大人たちが出会ったからこそ生まれた「こどもびいる」。
子どもから大人まで誰もが楽しむことができる、これまでにない飲みものとして広がっていきます。
そうですね。懐かしいですね。一般のお客様からもお礼の手紙が届いたんですよね。昔から飲料を作ってきましたが、お礼の手紙がくるのは初めてでした。「帰省で孫が喜ぶのもこの商品のおかげです」と祖父の方や祖母の方からお便りを頂いて。最初はビールが飲めない女性の大人向けに作っているけど、商品は勝手におじいちゃんの商品になるし、おばあちゃんの商品になるし、子どもの商品になるし。そこは、もう開発者の意図とは関係なく(良い)商品は自分でね、一人立ちしていくものなんだなーと思いながら。
僕も、それまではジュースはジュース会社が、アイスはアイス会社がつくるものと思ってたけど、つくるプロが必ずしも商品を考えるプロではないんだなと。むしろ業界の中にずっといるからこそ見えていないものが多いんじゃないかと。僕と八智代が今のような仕事(デザイン、ブランディングを専門とする「デザイン事務所ウィロー」)を始めるきっかけにもなりました。
そうかもしれないですね。でもそれは意図してるわけではなく、たまたま浅羽さんと出会って、今もまだあの頃の延長線上にいる感じなんですよね。歴史上、技術と経営この両輪がかみ合って初めて大きな事業として価値を生んだ経営者たちは大勢いますよね。私は勝手に自分と浅羽さんも、そんな関係になれればいいなと考えているんです。

「こどもびいる」のギフトセットや専用ジョッキ、栓抜きなど「こどもびいる」は成長期の子どものようにぐんぐんと育っていきます。
特許庁は「どこの分類にも入れられない」と「こどもびいる」のために新しい分類を設けるほどでした。
それはもう小さい頃から、祖父や父から言われ続けてきたことだから。それはもう、そうせないかんとかじゃなく、当たり前になっていると思います。それはもう友桝飲料のDNAだと思います。できたら人がやってないのをやろうと。なんで、そうなったのかは分からないです。もう、それがいいんです(笑)。誰かが通ったあとはお手本もある、誰もやっていないことをやるのはリスクがありますが、やらない理由にはなりません。だから自分は、それまでにない(のちのODM事業となる)事業をやろうと。誰もやったことないことをやって成功するに越したことはないですが、失敗も良しとしようということはあります。ま、失敗して会社を潰してしまってはいけませんけども、そこは見極めながら、ですね。(笑)
僕は失敗を恐れて、データ集めたりマーケットのリサーチして皆で多数決で決めたり…とか、そういう風になっちゃうことの方が怖い。まぁ「ヒット商品を作ろうとしてこう考えて作った」って言えたらカッコイイかもしれないけど、僕らはそうじゃない(笑)。それじゃ「こどもびいる」は絶対生まれなかったし。あたりまえのことなんだけど、楽しい商品を作るには、作ってる側が誰よりも楽しまないといけないんだよね。
そうですね。浅羽さんは、いつも子どもみたいな自由な発想を持って、遊び心を形にする人です。これからも友桝飲料の両輪の一つとして、よろしくお願いします。
「こどもびいる」誕生から12年、
浅羽さんと友桝飲料が出会ってから14年。
歴史に名を刻む名コンビになる日まで、
のみもののよみものは続きます。
ちなみに、「こどもびいる」のラベルに
描かれた浅羽さんの子どもたちは、
今年でもう大学生。
夢が叶う日も遠い未来ではなさそうです。


神奈川県・小田原市は、温暖な気候と海に面した地形、 富士山の火山灰による水はけの良い土壌に恵まれている地域で、 昔から柑橘栽培が盛んな地域でした。 ここで生まれ、小田原の名物となっているのが「片浦レモンサイダー」です。 このサイダー、実は二宮金次郎生誕の地だからこそ生まれたサイダーなのです。

「カラン、カラン」とビー玉を鳴らしながら飲む、ラムネ。 夏の風物詩であるラムネが時代とともに減りつつある今、 ひそかに若い人達の間で人気を集めているのが、「フルーラ」です。 それは式を控えた花嫁さん達の手によって広がっていったのですー

清らかな水源に恵まれた蛍の名所、佐賀県小城市。 自然豊かなこの場所に、友桝飲料の本社工場はあります。 ここには、炭酸のこれまでとこれからが詰まっていました。 シュワシュワと消えてなくなる炭酸に込めた消えない想いとは…

福岡の都心からフェリーでわずか10分のところにある、能古島。 この島で愛され続けている地サイダーが「能古島サイダー」と 「nocorita」です。そこには地震にも負けない、 島の小さなカフェから生まれた物語がありました…

全国のレストランやバーなどで多くの支持を得ている プロバーテンダー岩永大志さん監修の「n.e.o」シリーズ。 開発するにあたり、岩永さんが足繁く通った場所、 それは、博多の小さな老舗ソース工場でした…

あざやかな緑色のソーダにソフトクリームが浮かぶ。 昔ならどこの喫茶店でもお目にかかれた、クリームソーダ。 最近では、あまり見かけなくなったあの懐かしい味が Café&Meal MUJIにあるのです。昔とどこが違うかというと…

砂蒸し温泉施設、ホテル、JR九州「特急・指宿のたまて箱」など 指宿はもちろん全国各地に広がっている「指宿温泉サイダー」。 発案者は、長崎県出身、西郷さん似の?倉本さん。 ある日、指宿ならではの手土産がないことに気がついて…

「こどもだって飲まなきゃ、やってらんねーよ」 というキャッチコピーで飲料界にデビューしたのは、 見た目はビール、中身はリンゴ!の「こどもびいる」。 実は、こどものためのびいる、じゃなかったようで…

現在準備中です。