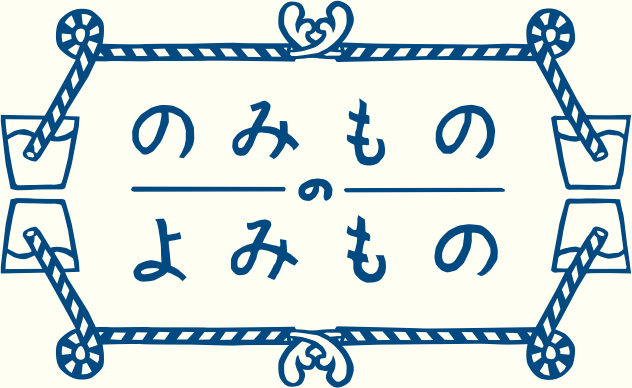
二宮金次郎といえば、校庭にある薪を背負い本を読む少年の像ですがー
では実際、何をした人?と聞かれると答えられる大人は少ないかもしれません。
今回ご紹介する「片浦レモンサイダー」は、そんな二宮金次郎の生誕の地、
神奈川県・小田原だからこそ生まれた地サイダー、いえ、地域振興サイダーなのです。

報徳二宮神社

友桝飲料

(幼名・二宮金次郎)


神奈川県の西部に位置する小田原市は、南には相模湾、西には箱根山を抱えた位置にあります。東京から新幹線で約30分、箱根までは車で約30分、かつては小田原城の城下町として栄えた街が今回の舞台です。当時、「片浦レモンサイダー」の担当だった友桝飲料の原田取締役と向かった先は、小田原城のすぐ隣りにある報徳二宮神社。宮司である草山明久さんが出迎えてくれました。
こんにちは。ご無沙汰しております。今日はよろしくお願いいたします。
お久しぶりです。直接、こうしてお話をするのは何年ぶりですかね?
えー、10年ぐらいですね。今日は片浦レモンサイダーの開発時のことを振り返りながら、色々とお話を伺いたいんですが、僕が入社して2年目で全てが初めてのことだらけで。実はあまりに必死だったので記憶がないんですよね(笑)。そもそも、なぜ宮司さんである草山さんが「小田原柑橘倶楽部」の創設に関わり、地サイダーを作ろうと思ったんですか?
ここ、報徳二宮神社は二宮尊徳(幼名:二宮金次郎)を奉る神社です。尊徳先生は江戸末期に小田原に生まれ、藩からの助成金に頼ることなく自らが再興した田畑や財産を売り、これを現代でいう基金や資本金にして生涯で600にも及ぶ農村復興や財政再建を成し遂げた方です。二宮尊徳翁には「一円融合」という思想があります。

世の中に存在する全ての物や人には「徳」(長所・美点・価値など)がもともと備わっているのだから、たとえ対立する物事(思想・善悪・貧富・強者弱者など)であっても、切り離して考えるのではなく、あらゆる全ての物事を常に一つの円の中に入れて考え、万物が共存共栄することができる、いつまでも心豊かに暮らせる社会(地域・国・世界)を目指すことが大切だという教え。



地元のいろんな業種の方々と共に柑橘農家さんを応援しようと「小田原柑橘倶楽部」が生まれたのも、この考えがベースにあったからなんですね。
そうです。江戸末期は自然災害や幕藩体制の衰退により低迷していた時代、ちょうど現代と状況的には似ているんじゃないかなと思っています。
確か…片浦レモンサイダーができたのも東北の震災が起きた後でしたね。
こちらでも多くの被害が出ました…すべてが止まってしまって。そんな時に地サイダーの存在を知ったんです。これだと思いましたね。
でも、なんでまたサイダーだったんですか?
実は、それまでは小田原柑橘倶楽部ではみかんを売っていたんです。小田原は柑橘農家さんが多い地域で。糖度が高くおいしいのに、表皮にキズがあるというだけで市場では取引されない。そんなみかんを廃棄するのではなく、家庭用として販売しようと段ボールも家庭用を想定したサイズのものをオリジナルで作り、4色刷りのパッケージデザインで売り出したんです。ただ、旬の間の1ヶ月で売り切らないといけないという大きな壁がありました。サイダーなら「小田原のみんなの特産品」として地元で広く販促していけると思ったんです。



賞味期限も1年はありますから、安心かもしれませんね。当時から片浦レモンサイダーの構想は決まっていたように思いますが、片浦レモンは小田原の特産品だったんですか?
いいえ、当時はまだ無名に近い存在で。片浦レモンは、オレンジの自由化が始まり輸入のレモンが多く出回っていた頃に、安心で安全な国産のレモンを食べたいという声に応えて30年以上もの間、片浦地域の柑橘農家さん達が研究を重ねて低農薬で栽培されてきたものです。農薬散布も1度のみ。ノーワックスで防カビ剤も不使用。レモンはとてもデリケートなので風で枝葉が果実に当たるとそこに黒いキズ跡ができてしまいます。味は変わらず素晴らしいのですが、そのままでは市場に流通させることができません。ですから、片浦レモンの果汁を活用したサイダーなら…と思ったんです。
なるほど。果汁なら見た目は関係ないですし、サイダーなら冷蔵庫がない場所でも保存もできます。売り場も気軽に取り入れやすいんでしょうね。
そうなんです。それで地元の炭酸メーカーに問い合わせてみたところ、小ロットで製造できる佐賀の友桝飲料を紹介されて。最初は果汁を送るのにも「小田原柑橘倶楽部」のみんなで作業場に一日中こもってレモンを一つひとつ、手で絞って果汁を集めて佐賀に送っていました。みんなで手分けして丸1日は作業してたかな。さすがに今は工房で搾汁していますが(笑)
え、一つひとつ、手で絞ってたんですか!いやー、かなりの量を手絞りされてたんじゃないですか。確か、発売前からしっかり販促先を決めていただいていて。特産物があるからサイダー作るって方は多いんですよ。でもここまでちゃんと人を巻き込んで販促先を決めてから依頼される方という方は意外と少ないんです。初回から1000ケースは生産してたんじゃないでしょうか。
ええ、そうですね。農家さん、酒屋さん、地元のホテル、いろんな業種の方々が「自分たちのサイダーを作ろう」となり、多くの出資や販売協力を得まして形にすることができました。関わる人が大勢いる分、大変な面も増えていくんですが、地域で「人と物とお金」を循環させていくーそれが小田原柑橘倶楽部の目的でしたから。今は、耕作放棄地を開墾して片浦レモンの苗木を植えて育てています。農業の担い手も減っていく一方ですから、若手の農家さんに管理していただいて、安心して働ける場を提供できればと思っています。
まさに「一円融合」ですね。小田原の人たちが切磋琢磨することで「自分たちのサイダーだ」と自信を持って勧められる。だからこそ、地元にこのサイダーが根付いたんでしょうね。





小田原の江之浦と根府川を含む片浦地区で収穫された片浦レモン。太陽の光と潮風を浴びて低農薬で栽培されています。収穫シーズンは11月から4月中旬まで。この日、片浦レモンの畑を案内してくれたのはレモン農家の横森幹詞さん。脱サラして2年前より小田原柑橘倶楽部の畑を管理しています。将来の夢はご夫婦でカフェをされることなのだとか。スマホにはおすすめの片浦レモンパスタの写真が。

片浦レモンサイダーが発売される当時の広告を今でも覚えているという株式会社かのや今井本店の柴崎唯さん。柴崎さんは、片浦レモンサイダーの卸を行う商店の一つです。「小田原の特産品と言えば、片浦レモンサイダー。みんな知ってるよ。小田原や箱根では普通にコンビニでも買えるよ。もう、そろそろ王冠を栓抜きなしで開けられるスクリューにするとか、新しい変化が欲しいね。よろしく、友桝飲料さん(笑)」
片浦レモンサイダーの王冠には「一円融合」の文字が記されています。
二宮尊徳の想いが小田原の人々に引き継がれ、
その後も「小田原みかんサイダー」「小田原梅サイダー」、さらには「片浦レモンの生ようかん」と広がりを見せます。
しかし、草山さんは生産量アップやシリーズ展開が目的ではないと語ります。